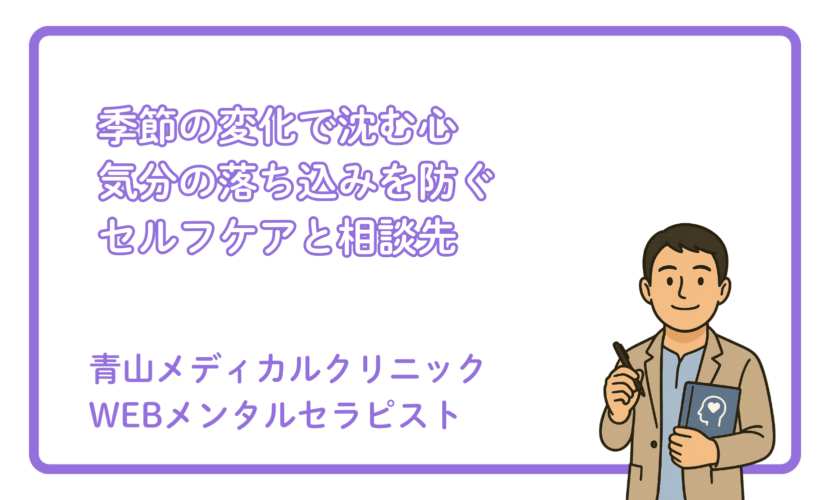目 次
はじめに
春から夏、夏から秋へ――季節が変わる時期に「なんとなく気分が落ち込む」「やる気が出ない」と感じる方は少なくありません。
これは単なる気の持ちようではなく、気温・気圧・日照時間などの変化によって 自律神経やホルモンバランスが乱れることが原因 です。
本記事ではメンタルセラピストの視点から、季節の変わり目に起こりやすい心の不調の特徴と、その対処法 をわかりやすくお伝えします。
季節の変わり目に気分が落ち込みやすい理由
気圧と天候の変化
低気圧や天候不順は自律神経に負担をかけ、倦怠感や気分の落ち込みを招きます。
日照時間の変化
日光を浴びる時間が減ると「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンの分泌が低下し、気分が不安定になります。
生活リズムの乱れ
新年度や新しい環境の変化により、睡眠不足や不規則な生活が続きやすくなります。
気分の落ち込みに見られるサイン
身体的サイン
眠りが浅い、早朝に目が覚める
頭痛や肩こりが増える
食欲が落ちる、または過食になる
心のサイン
やる気が出ない
イライラしやすい
何をしても楽しめない
これらが続くと「季節性うつ」の一因になることもあるため、早めの対処が重要です。
気分の落ち込みを和らげるセルフケア
1. 朝日を浴びる
起床後にカーテンを開けて自然光を取り入れる
セロトニンの分泌が促され、体内時計が整いやすい
2. 適度な運動を取り入れる
ウォーキングやヨガなど軽めの運動が効果的
血流改善により気分が前向きになります
3. 栄養バランスを整える
トリプトファン(大豆製品、バナナ、乳製品)はセロトニンの材料
ビタミンB群、鉄分も神経の働きをサポート
4. 睡眠環境を整える
就寝前のスマホを控える
寝室を暗く涼しく保ち、眠りやすい環境にする
5. リフレッシュの工夫
香り(アロマ)や音楽でリラックス
カラフルな服や小物を身につけて気分転換
👉 「気分の落ち込みは仕方ない」と我慢せず、早めの相談が安心です。
青山メディカルクリニックでは、心身の不調に関するご相談を幅広く承っております。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
まとめ
季節の変わり目は、心も体も環境の影響を受けやすい時期です。
大切なのは、
光・運動・食事・睡眠の4本柱を整えること
不調を「性格の問題」とせず、体からのサインと考えること
つらさが続くときは専門家に相談すること
です。小さなセルフケアの積み重ねが、気持ちを軽やかに整える第一歩となります。
👉 気分の不調が続く場合は、一人で抱え込まず専門医へご相談ください。
青山メディカルクリニックが、あなたの心身の回復をサポートします。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 季節の変わり目の気分の落ち込みはうつ病ですか?
A. 全てがうつ病ではありません。生活リズムや気象の影響が大きいですが、長引く場合は専門の相談をおすすめします。
Q2. サプリメントで改善できますか?
A. ビタミンB群やトリプトファンを含む食品・サプリはサポートになりますが、生活習慣の見直しが基本です。
Q3. どのくらいの期間続いたら受診すべきですか?
A. 2週間以上改善しない場合、医師への相談が望ましいです。
Q4. 運動が苦手ですがどうすればいいですか?
A. 軽いストレッチや散歩でも十分です。体を少し動かすだけで気分が変わります。
Q5. 日光を浴びるのが難しい日は?
A. 室内照明を明るくする、光療法ランプを利用するなども有効です。
👉 気分の落ち込みでお困りの方へ。
青山メディカルクリニックは、患者様一人ひとりに合わせたケアを大切にしています。
今すぐご予約いただき、安心のサポートを受けてください。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
引用・参考文献
厚生労働省 e-ヘルスネット「気分障害」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-007.html
免責・署名
本記事はAIによるデータ収集をもとに作成された一般的な情報提供記事です。
最終チェックは人間(専門スタッフ)が行い、表現・正確性・コンプライアンスを確認しております。
効果には個人差があり、副作用やリスクについては必ず医師にご相談ください。
また、記事内容は国内外の情勢や関係省庁の指導、その他の想定外の事象や不可抗力、天災等により変更・修正される場合があります。
私たちは、患者様を助けたい・幸せにしたいという願いを大切にしています。
ただし医療には限界もあります。その点をご理解いただきながら、温かい目線でお読みいただければ幸いです。
執筆:WEBメンタルセラピスト(心の健康維持に役立つ情報を届ける)
Content Production by DOLCE©︎
【資格一覧】
情報・法務系:個人情報保護士/知的財産保護士/インターネットコミュニケーションアドバイザー
心理・セラピー系:メンタルセラピスト/カラーセラピスト/足踏みマッサージ師
栄養・生活系:サプリメント管理士/食生活アドバイザー
医療・薬学系:薬学アドバイザー/美容薬学アドバイザー
お問い合わせ先
青山メディカルクリニック
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目10-21
T’S BRIGHTIA 南青山 EAST 1F
電話番号:03-6434-7118
公式HPお問い合わせ:https://helpdog.ai/f/amclinic/form_4be8f33d
LINE予約:https://amclinic.tokyo/line-reservation
WEB予約:https://amclinic.tokyo/web-reservation
担当部署:事業戦略部・広報部
受付時間:月・火・水・金・土 10:00~18:00