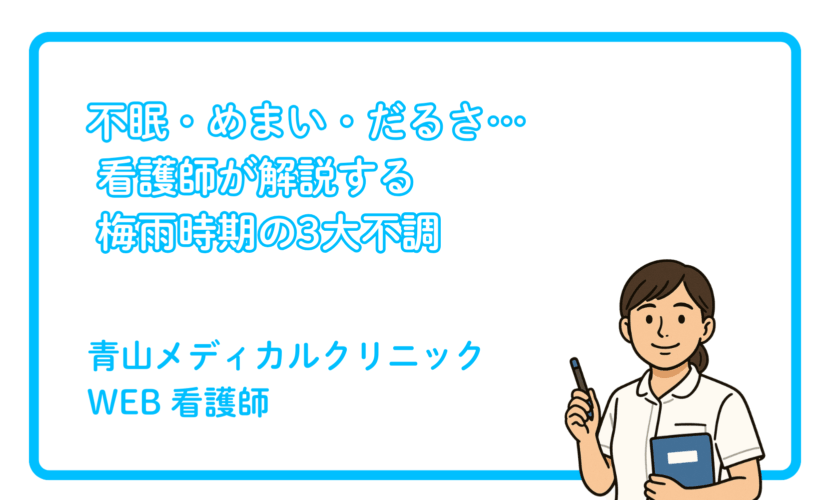目 次
はじめに
梅雨の季節になると「体がだるい」「頭痛が増える」「むくみやすい」といった体調不良を訴える方が多くなります。
これは単なる気分の問題ではなく、気圧や湿度、気温の変化が体に大きな負担を与えているため です。
本記事では、看護師の視点から 梅雨時期に増える体調不良の原因とセルフケアの方法 をわかりやすく解説します。
梅雨に増える代表的な体調不良
頭痛
低気圧によって血管が拡張し、神経を刺激するために起こりやすくなります。
むくみ
湿度が高いと体内の水分代謝が滞り、脚や顔がむくみやすくなります。
だるさ・倦怠感
自律神経の乱れにより、体が常に緊張状態になり疲れが抜けにくくなります。
胃腸の不調
湿気で消化機能が低下し、食欲不振や下痢を起こすこともあります。
なぜ梅雨に不調が増えるのか?
気圧の低下
気圧が下がると自律神経が乱れ、血流やホルモン分泌に影響します。
湿度の高さ
汗が蒸発しにくく、体温調整が難しくなるため疲労感が増します。
寒暖差
日によって大きな気温差があり、体が適応できず不調につながります。
セルフケア① 食事で整える
水分補給
常温の水や麦茶をこまめに飲む
冷たい飲み物のとりすぎは胃腸を冷やすため注意
栄養バランス
ビタミンB群(豚肉、卵、納豆):疲労回復
鉄分(赤身肉、ほうれん草):酸素を体に届ける
カリウム(バナナ、きゅうり):余分な水分を排出
セルフケア② 運動で巡りをよくする
軽いウォーキングやストレッチで血流改善
湿度で重くなった体をリフレッシュ
筋肉を動かすことで自律神経が整いやすくなる
セルフケア③ 睡眠環境を整える
就寝前のスマホを控え、眠りの質を守る
寝具を通気性のよいものに替える
エアコンは除湿モードで快適に保つ
セルフケア④ 気分転換の工夫
アロマ(ペパーミント、ラベンダー)でリラックス
明るい色の服や小物を取り入れて気分をアップ
音楽や趣味に触れる時間をつくる
👉 不調を我慢せず、早めにケアを始めましょう。
青山メディカルクリニックでは、季節性の体調不良に関するご相談を承っております。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
まとめ
梅雨の体調不良は「季節のせいだから仕方ない」と片付けてしまいがちですが、適切なセルフケアで軽減することが可能です。
特に大切なのは、
水分・栄養を意識した食事
軽い運動で血流改善
睡眠環境の調整
気分転換の工夫
です。心身を整える小さな習慣が、不調を和らげる第一歩になります。
👉 体調不良が続く場合は、早めに受診して安心を。
青山メディカルクリニックが、あなたの健康をサポートします。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 梅雨の不調は誰にでも起こりますか?
A. はい。特に女性や自律神経が乱れやすい方は影響を受けやすいです。
Q2. サプリメントで予防できますか?
A. 栄養補助としては役立ちますが、基本は食事・運動・睡眠のバランスを整えることです。
Q3. むくみを改善する簡単な方法は?
A. 足を心臓より高くして休む、軽いストレッチ、カリウムを含む食材を摂ることが有効です。
Q4. 頭痛が続くときはどうすれば?
A. 我慢せず医師にご相談ください。片頭痛や他の病気が隠れている可能性もあります。
Q5. 気分の落ち込みも梅雨のせいですか?
A. 天候による自律神経の乱れで気分が不安定になることがあります。長引く場合は専門家にご相談ください。
👉 小さな不調も早めにご相談を。
青山メディカルクリニックでは、生活習慣や体質に合わせたケアをご提案しています。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
引用・参考文献
厚生労働省 e-ヘルスネット「気象と健康」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/heart/k-02-010.html
免責・署名
本記事はAIによるデータ収集をもとに作成された一般的な情報提供記事です。
最終チェックは人間(専門スタッフ)が行い、表現・正確性・コンプライアンスを確認しております。
効果には個人差があり、副作用やリスクについては必ず医師にご相談ください。
また、記事内容は国内外の情勢や関係省庁の指導、その他の想定外の事象や不可抗力、天災等により変更・修正される場合があります。
私たちは、患者様を助けたい・幸せにしたいという願いを大切にしています。
ただし医療には限界もあります。その点をご理解いただきながら、温かい目線でお読みいただければ幸いです。
執筆:WEB看護師(医療現場の経験をもとに施術やケアをわかりやすく解説)
Content Production by DOLCE©︎
【資格一覧】
情報・法務系:個人情報保護士/知的財産保護士/インターネットコミュニケーションアドバイザー
心理・セラピー系:メンタルセラピスト/カラーセラピスト/足踏みマッサージ師
栄養・生活系:サプリメント管理士/食生活アドバイザー
医療・薬学系:薬学アドバイザー/美容薬学アドバイザー
お問い合わせ先
青山メディカルクリニック
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目10-21
T’S BRIGHTIA 南青山 EAST 1F
電話番号:03-6434-7118
公式HPお問い合わせ:https://helpdog.ai/f/amclinic/form_4be8f33d
LINE予約:https://amclinic.tokyo/line-reservation
WEB予約:https://amclinic.tokyo/web-reservation
担当部署:事業戦略部・広報部
受付時間:月・火・水・金・土 10:00~18:00