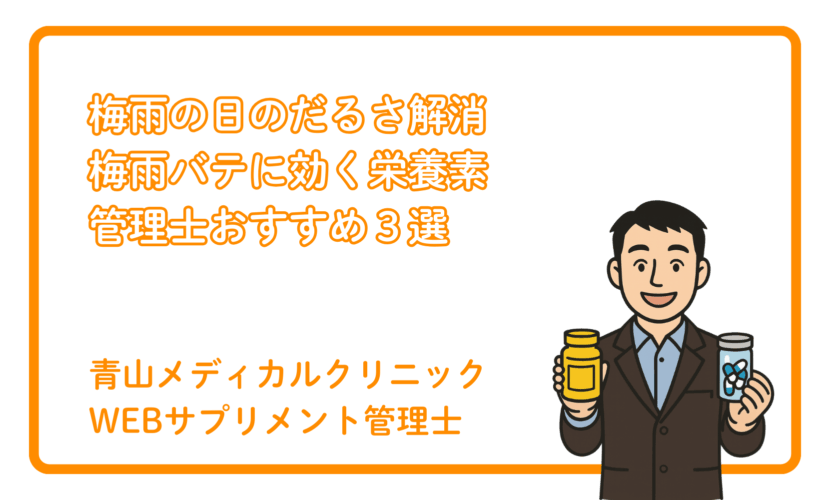目 次
はじめに
梅雨の時期になると「体が重い」「眠気が続く」「朝スッキリ起きられない」と感じる方が増えます。
これは、湿度や気圧の変化による自律神経の乱れや、体内の水分代謝の滞りが原因とされています。
本記事では、サプリメント管理士の視点から 梅雨のだるさ対策に効果的な3つの栄養素 を紹介し、日常に取り入れやすい食材やサプリ活用のポイントを解説します。
梅雨のだるさの原因とは?
高湿度による水分代謝の低下
体内に余分な水分がたまり、むくみやだるさの原因になる
「気象病」とも呼ばれ、天候により不調が出やすい
自律神経の乱れ
気圧の変化で交感神経と副交感神経のバランスが乱れる
疲労感や集中力低下、気分の落ち込みが起こりやすい
睡眠の質の低下
蒸し暑さで眠りが浅くなり、疲労回復が不十分になる
栄養素① 鉄分(酸素を全身に届ける)
不足するとどうなる?
鉄分が不足すると血液中の酸素運搬が滞り、だるさ・息切れ・頭痛などが出やすくなります。特に女性は月経の影響で不足しやすい栄養素です。
食材例
赤身肉(牛・豚)
レバー
ほうれん草
ひじき
サプリ活用のポイント
「ヘム鉄(動物性由来)」は吸収率が高い
ビタミンCと一緒に摂ると吸収がアップ
過剰摂取は便秘や胃腸障害の原因になるため、用量を守ること
栄養素② ビタミンB群(エネルギー代謝を助ける)
不足するとどうなる?
糖質・脂質・タンパク質をエネルギーに変換する働きを担っており、不足すると「疲れやすい」「集中力が落ちる」といった症状が出やすくなります。
食材例
豚肉
卵
納豆
玄米
サプリ活用のポイント
複数のビタミンB群は「チーム」で働くため、マルチビタミンタイプを選ぶと効率的
水溶性なので、余分に摂取した分は尿から排泄されやすい
栄養素③ カリウム(余分な水分を排出する)
不足するとどうなる?
体内のナトリウムと水分バランスを調整し、むくみやだるさを防ぎます。不足すると倦怠感や筋肉のけいれんが出やすくなります。
食材例
バナナ
キュウリ
スイカ
枝豆
サプリ活用のポイント
サプリでの過剰摂取は腎臓に負担をかけることがあるため、基本は食事からの摂取が安心
高血圧の薬(降圧利尿薬など)を服用中の方は医師に相談が必要
栄養素を取り入れる食事の工夫
朝食でエネルギー補給
例:豚肉と野菜の味噌炒め+ごはん+バナナ
→ ビタミンB群+カリウムが補える
昼食でたんぱく質を意識
例:牛赤身ステーキ+サラダ+玄米
→ 鉄分+ビタミンB群が豊富
夕食は消化のよいバランスを
例:枝豆+冷奴+魚の煮つけ+みそ汁
→ カリウム+鉄分+タンパク質が取れる
👉 食事やサプリでの栄養補給は、早めに始めることが大切です。
青山メディカルクリニックでは、栄養指導や体調に合わせたサプリメント相談を行っています。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
まとめ
梅雨のだるさは「湿気や気圧のせいだから仕方ない」と思われがちですが、栄養の取り方次第で軽減できます。
特に大切なのは、
鉄分(酸素を運ぶ)
ビタミンB群(代謝を助ける)
カリウム(水分バランスを整える)
の3つの栄養素です。
👉 だるさや疲労感が続く場合は、我慢せず受診を。
青山メディカルクリニックが、あなたの健康を栄養面からもサポートします。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 栄養素は食事だけで十分ですか?
A. 軽度の不調なら食事で改善できることもありますが、不足しがちな場合はサプリで補うのも有効です。
Q2. カリウムのサプリは安全ですか?
A. 健康な方なら少量は問題ありませんが、腎臓病や降圧薬を使用中の方は注意が必要です。
Q3. 梅雨バテ対策におすすめの飲み物は?
A. 常温の水や麦茶、経口補水液がおすすめです。清涼飲料水は糖分が多いため控えめにしましょう。
Q4. 鉄分サプリはどのくらいで効果が出ますか?
A. 個人差はありますが、数週間〜数か月継続することで効果を感じやすくなります。
Q5. ビタミンB群はいつ飲むのが良いですか?
A. 水溶性なので食後に分けて摂るのがおすすめです。
👉 栄養相談やサプリ選びに迷ったら、専門家にご相談ください。
青山メディカルクリニックでは、管理栄養士と連携した栄養指導を行っています。
LINE予約はこちら|WEB予約はこちら
引用・参考文献
厚生労働省 e-ヘルスネット「ビタミン・ミネラル」
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/vitamin/
免責・署名
本記事はAIによるデータ収集をもとに作成された一般的な情報提供記事です。
最終チェックは人間(専門スタッフ)が行い、表現・正確性・コンプライアンスを確認しております。
効果には個人差があり、副作用やリスクについては必ず医師にご相談ください。
また、記事内容は国内外の情勢や関係省庁の指導、その他の想定外の事象や不可抗力、天災等により変更・修正される場合があります。
私たちは、患者様を助けたい・幸せにしたいという願いを大切にしています。
ただし医療には限界もあります。その点をご理解いただきながら、温かい目線でお読みいただければ幸いです。
執筆:WEBサプリメント管理士(正しいサプリ知識を発信し生活習慣改善をサポート)
Content Production by DOLCE©︎
【資格一覧】
情報・法務系:個人情報保護士/知的財産保護士/インターネットコミュニケーションアドバイザー
心理・セラピー系:メンタルセラピスト/カラーセラピスト/足踏みマッサージ師
栄養・生活系:サプリメント管理士/食生活アドバイザー
医療・薬学系:薬学アドバイザー/美容薬学アドバイザー
お問い合わせ先
青山メディカルクリニック
〒107-0062 東京都港区南青山3丁目10-21
T’S BRIGHTIA 南青山 EAST 1F
電話番号:03-6434-7118
公式HPお問い合わせ:https://helpdog.ai/f/amclinic/form_4be8f33d
LINE予約:https://amclinic.tokyo/line-reservation
WEB予約:https://amclinic.tokyo/web-reservation
担当部署:事業戦略部・広報部
受付時間:月・火・水・金・土 10:00~18:00